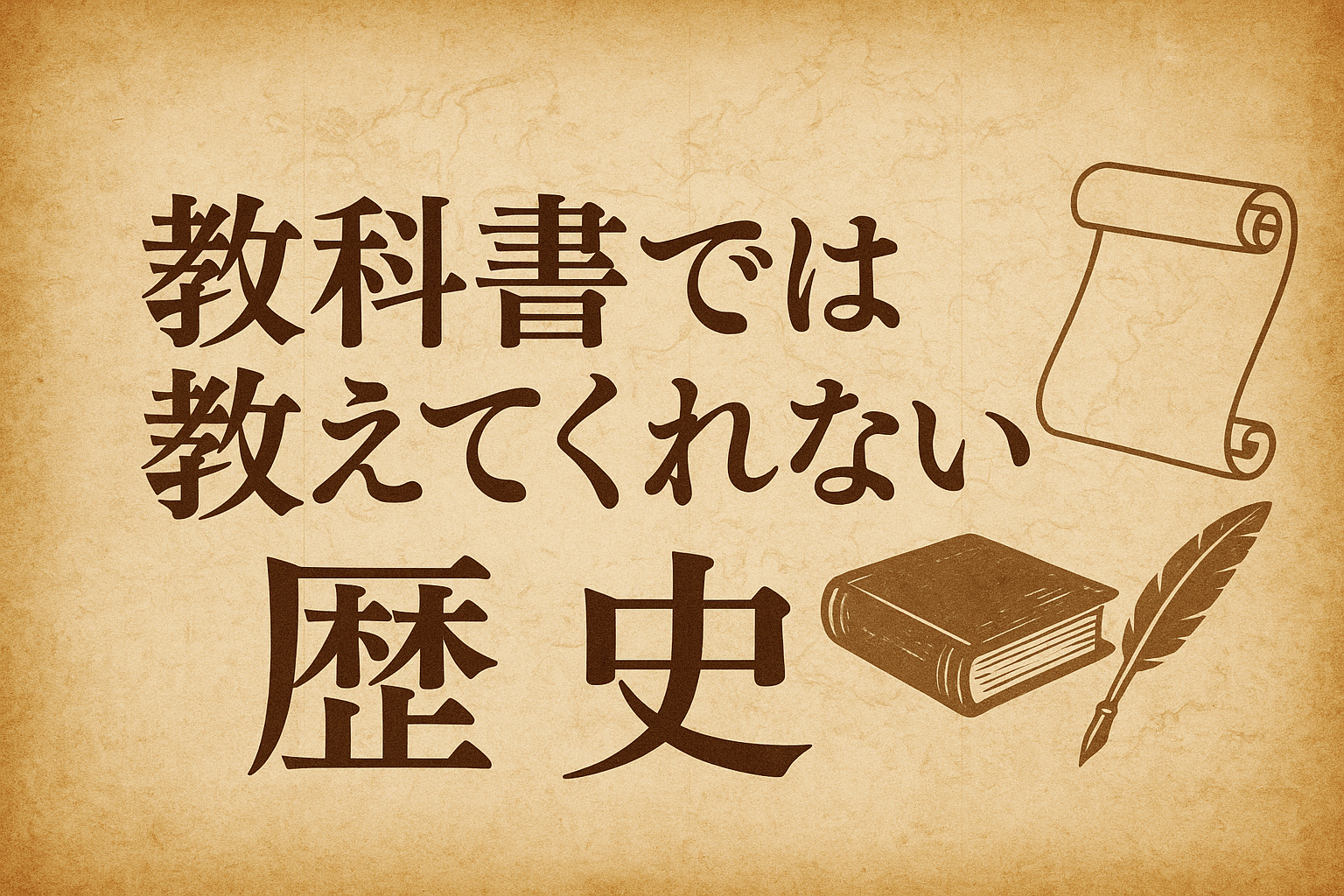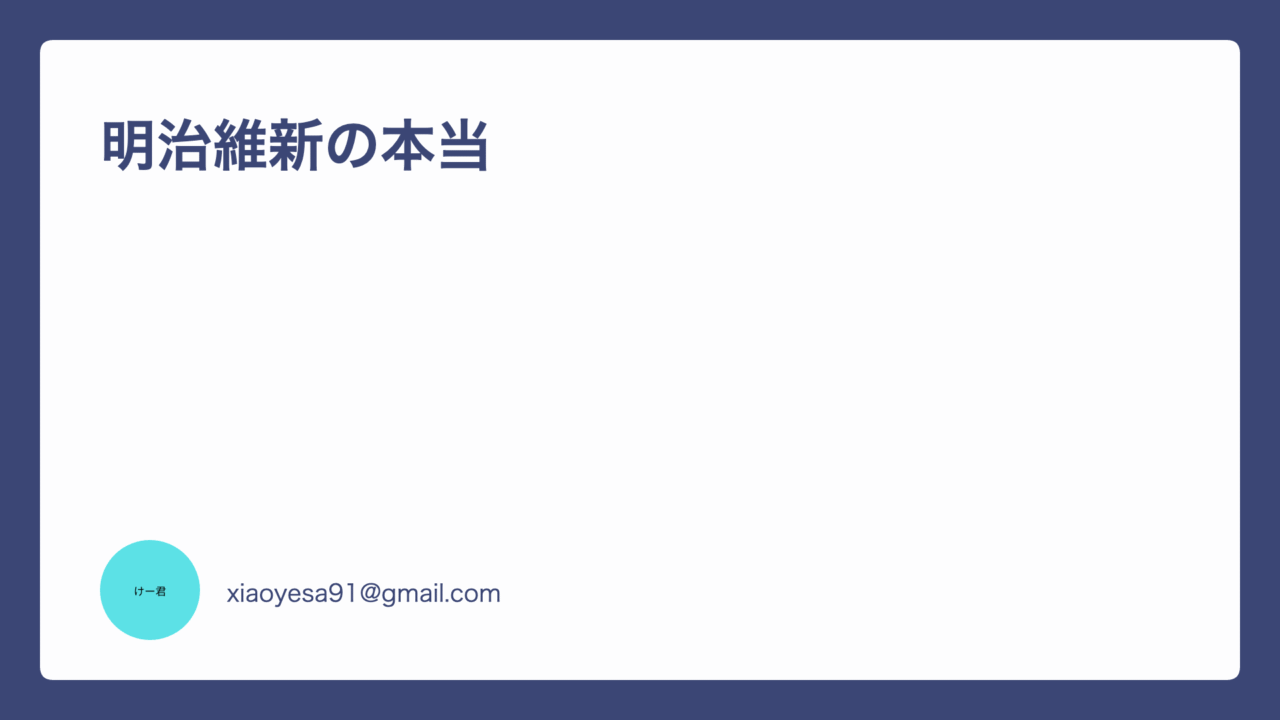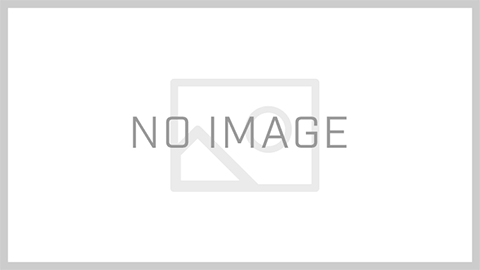私たちが習う明治維新
明治維新についての一般的な歴史の教科書には
「鎖国を敷いていた徳川幕府に対しペリーが黒船を率いて来日。日米和親条約の締結により200年以上続いた鎖国からの開国。弱体化した徳川幕府に危機感を覚えた薩摩藩、長州藩が討幕を行い大日本帝国を誕生させた」
上記のような記載の仕方をしている事が多いですが本当は少し違います。
本当は薩長が実権を握ろうとしたクーデター
明治維新は薩長が実権を握るために起こしたクーデターです。
当時の徳川幕府は尊王開国派です。
翻って薩長は当初尊王攘夷派でしたが薩英戦争を経て外国勢力の強大な軍事力を目の当たりにし、尚且つイギリスとの協力関係を進めたことで薩長も尊王開国派に転換していきました
「尊王(そんのう)」とは、
日本の伝統的な思想で「天皇を敬い、その権威を大切にする」という考え方を指します。特に有名なのは 江戸時代後期から幕末 にかけての「尊王攘夷(そんのうじょうい)」というスローガンで、
- 尊王:天皇を中心に政治を行うべきだとする思想
- 攘夷:外国勢力を排除すべきだとする思想
薩長が徳川幕府を倒す理由が消滅した
徳川幕府と薩長も同じ尊王開国派になった事とで徳川幕府を倒す理由が消滅していました。
**尊王開国派(そんのうかいこくは)**とは、江戸時代末期(幕末)において、
- **天皇を尊ぶ(尊王)**思想を掲げつつ
- **外国と積極的に交流・通商を行う(開国)**ことを主張した人々や政治的立場を指します。
慶應3年10月14日の大政奉還によって徳川幕府は自ら単独政権を廃止し、公武合体・公議政体の新体制樹立を進めようとしました。
そのため薩長を中心とした討幕勢力の中には幕府討幕の大義名分が無くなっていました
公武合体とは、江戸時代末期(幕末)において、
- **「公」=朝廷(天皇・公家)**と
- 「武」=幕府(将軍・武士)
が協力・連携し、政治体制を維持・安定させようとした政策や考え方を指します。
なぜ旧幕府討伐の戊辰戦争は起きたのか
慶應3年12月9日、岩倉具視を首班とする雄藩五藩によるクーデターにおいて王政復古の大号令により朝廷が掌握されました。
王政復古の大号令とは、
1867年(慶応3年)12月9日 に発せられた宣言で、
- 天皇中心の新政府を樹立することを宣言し、
- 江戸幕府を正式に廃止した歴史的出来事です。
これにより徳川家に対し内大臣辞職と領地の返納を求めるといった圧力をかけましたが徳川慶喜が強く拒否し会津藩や桑名藩等佐幕派急進勢力を抑え、土佐藩、越前藩らの公議政体派の動きもあり、要求は撤回されて衝突は一時回避されました。
しかし薩長は是が非でも衝突に持ち込みたかったため江戸において幕府側に挑発行為を行い江戸市中警護の任を受けていた庄内藩を襲撃します
旧幕府側は反撃として「薩摩藩邸焼き討ち事件」が起こします
薩摩藩邸焼き討ち事件とは、
1867年(慶応3年)12月25日、江戸にあった薩摩藩の藩邸が旧幕府側の兵士によって焼き討ちされた事件です。
これは 王政復古の大号令(12月9日) 直後に起きた騒乱で、戊辰戦争前夜の直接的な引き金の一つとなりました。
それに呼応し慶應4年1月2日幕軍の軍艦が兵庫沖に停泊中の薩摩藩軍艦へ砲撃を行い旧幕府側勢力と薩長は戦闘状態になり鳥羽・伏見の戦いが開始され戊辰戦争が始まりました
🏯 鳥羽・伏見の戦い(とば・ふしみのたたかい)
概要:
鳥羽・伏見の戦いは、1868年(慶応4年/明治元年)1月3日から6日にかけて、現在の京都市南部(鳥羽・伏見周辺)で起こった戦いです。
この戦いは、**戊辰戦争(ぼしんせんそう)の最初の戦いとして知られ、旧幕府軍と新政府軍(薩摩・長州・土佐など)**が衝突しました。🔥 戦いの経過
- 1868年1月3日: 旧幕府軍が鳥羽口から進軍。しかし薩摩軍の大砲により撃退。
- 同日夜~翌日: 伏見口でも戦闘が発生。新政府軍は西洋式の装備で優勢に。
- 1月5日: 朝廷が新政府軍に「錦の御旗(にしきのみはた)」を授ける。これにより旧幕府軍は「朝敵(ちょうてき)」とされ、士気が大きく低下。
- 1月6日: 旧幕府軍は大阪城へ退却し、徳川慶喜は船で江戸へ逃れる。
🏆 結果と影響
- 新政府軍の勝利。
- 徳川幕府は実質的に崩壊。
- 明治維新の流れが決定的になり、日本は近代国家への道を進み始めました。
⚔️ 戊辰戦争(ぼしんせんそう)
概要:
戊辰戦争は、1868年(慶応4年)から1869年(明治2年)にかけて行われた、旧幕府勢力と明治新政府軍との内戦です。
この戦争は、日本の政治体制を「江戸幕府」から「明治政府」へと移行させる決定的な戦いでした。
🏯 主な戦いの流れ
年・月 戦い 勢力・結果 1868年1月 鳥羽・伏見の戦い(京都) 新政府軍の勝利。戊辰戦争の開戦。 1868年3月〜5月 江戸開城(江戸無血開城) 勝海舟と西郷隆盛の交渉で江戸城が平和的に明け渡される。 1868年5月〜9月 奥羽戦争(北越戦争) 会津・庄内・長岡などが新政府軍と戦うが、敗北。 1869年5月 函館戦争(箱館戦争) 五稜郭に立てこもった榎本武揚・土方歳三ら旧幕府軍が降伏。戊辰戦争終結。
明治維新は薩長によるクーデターであり背後にはイギリス、旧幕府側にはフランスがいた
このように戊辰戦争の一連の流れを見ると朝廷をクーデターで掌握した薩長と公家が旧幕府勢力を朝敵に仕立て上げたのが明治維新の実態であります
そしてその背後には薩長の後ろ盾にいたイギリスと徳川の後ろ盾にいたフランスとの権益争いも絡んでいます
🇯🇵🤝🇫🇷 徳川幕府とフランスの関係
江戸時代の末期(幕末期)には、徳川幕府は西洋諸国と外交関係を結び始めました。その中でも**フランス(第二帝政期/ナポレオン3世の時代)**とは、特に深い関係を築きました。
🕰 背景:開国と西洋との交流
1854年の日米和親条約をきっかけに、日本は諸外国と次々に条約を結び、開国します。
幕府は欧米列強の中でも、技術・軍事力の高いフランスに強い関心を持ちました。
⚙️ 徳川幕府とフランスの主な関係
年 出来事 内容 1858年 日仏修好通商条約 幕府とフランスの間で正式な国交が開かれる。 1865年 フランス軍事顧問団の派遣 フランスから軍事顧問団が来日し、幕府陸軍(伝習隊)を近代化。 1867年 横須賀製鉄所の建設 フランス人技師ヴェルニー(L. Verny)が建設を指導。日本の近代工業の始まり。 1868年 戊辰戦争が勃発 フランス顧問団は旧幕府軍を支援したが、新政府軍勝利により撤退。 1869年 榎本武揚のフランス留学 旧幕府の人材も含め、新政府期にもフランスとの交流が続く。
⚔️ フランスと旧幕府軍の関わり
- 戊辰戦争の際、フランスの軍事顧問団(シャノワンヌ大尉、ブリュネ大尉など)は、旧幕府軍の訓練や軍制改革を担当していました。
- 戦争が始まると、彼らは中立を保つよう命令されましたが、一部は旧幕府軍に同情し、榎本武揚らとともに箱館(函館)まで行動したと伝えられています。
- しかし、戦後にはフランス政府が正式に彼らの行動を処分し、外交上の立場を保ちました。
🏗️ フランスの影響
- 軍事制度:近代式訓練、制服、武器の導入。
- 産業技術:横須賀造船所、灯台、鉄道技術など。
- 文化・教育:フランス語教育、法制度(ナポレオン法典の影響)など。
幕府滅亡後も、明治政府はフランスの技術・制度を取り入れ続け、日本の近代化に大きな役割を果たしました。
参考資料
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。